|
|
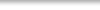 |
 |
介護保険を利用するには、利用したい方がどのくらいの介護が必要か審査する要介護認定を受けることからはじまります。65歳以上の方、または病気等により要介護状態になった40歳以上65歳未満の方が申請を行うと、状態により以下の認定を受けることになります。
要介護認定を受けるには、介護サービスを利用する本人、または家族が、市区町村の窓口で申請を行います。 |
|
![[1]申請します](img/service_1.gif) |
 |
 |
 |
 |
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定という市区町村からの認定が必要となります。認定してもらうためには、「介護保険の保険証」を添えて、「要介護認定申請書」を市区町村(市役所の「介護保険課」など)に提出します。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ※ |
申請は、本人または家族の他に、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設(千葉総合介護サービスでも可能)に代行してもらうこともできます。(詳しくは居宅介護支援サービスへ) |
|
 |
|
 |
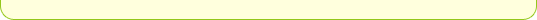 |
|
![[2]調査します](img/service_2.gif) |
 |
 |
 |
 |
保健師など、専門の知識をもつ職員が、家庭を訪問し、食事や歩行、入浴などの日常生活の状態、認知症の有無などを調査・確認します。基準は国で定められた一定のものです。
また、主治医にも疾病や心身の状態について、医学的な見地から意見をいただきます。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
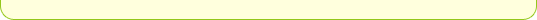 |
|
![[3]審査します](img/service_3.gif) |
 |
 |
 |
 |
調査結果と主治医の意見書をもとに区分(要介護度)を審査・判定します。もし、認定結果に不服がある場合には、千葉県の「介護保険審査会」に申し立てもできます。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
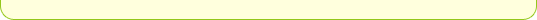 |
|
![[4]認定します](img/service_4.gif) |
 |
 |
 |
 |
必要な介護の度合いに応じて、「要介護度」を決定・通知します。この区分により、介護保険内で利用できるサービスの量なども決められます。(要介護度の一覧はこちら) |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
※「自立」(介護が必要ない)と認定された場合
介護サービス・新予防サービスは保険適用になりませんが、虚弱高齢者など要支援・要介護になる可能性のある方は、地域支援事業(介護予防事業)の対象となる場合があります。 |
 |
|
 |
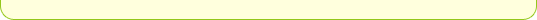 |
|
![[5]ケアプランを作成します](img/service_5.gif) |
 |
 |
 |
 |
本人またはその家族がどのようなサービスをどのくらい利用するかなどの計画を「ケアプラン」といいます。保険適用のサービスを利用するには、この「ケアプラン作成」が必要になります。(要介護度別ケアプランについてはこちら) |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
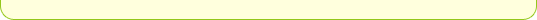 |
|
![[6]サービスを利用します](img/service_6.gif) |
 |
 |
 |
 |
ケアプランに沿い、サービスを利用した際には、サービス事業者にサービス費用の1割を支払います。また、いったん全額自己負担しなければならないサービスがありますが、申請により市区町村から9割分が支給されます。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
※施設での食事代・居住費は、1割の自己負担とは別になります。 |
 |
|
 |
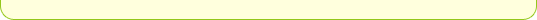 |
|
![[その他]更新申請を忘れずに](img/service_sonota.gif) |
 |
 |
 |
 |
有効期間は状況などによりますが、3ヶ月から24ヶ月(要支援は12ヶ月)までの間で定められています。期限後もサービスを利用したい場合は、更新の手続きが必要になります。
手続きは初めての申請と同じ手順となりますが有効期限の60日前から行うことができます。 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|